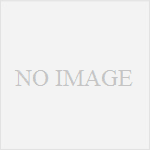近江国一宮 建部大社・滋賀県大津市神領

滋賀県大津市神領に鎮座する「建部大社(たけべたいしゃ)」
延喜式では式内社(名神大社)にして「近江国一宮」、旧社格は官幣大社です。
2015年(平成27年)には「琵琶湖とその水辺景観- 祈りと暮らしの水遺産」
の構成文化財として日本遺産に認定されました。
主祭神は本殿に「日本武尊(やまとたけるのみこと)」
権殿に「大己貴命(おおなむちのみこと)」の二柱を祀ります。
社伝では、日本武尊の死後の景行天皇46年、その妃「布多遅比売命(ふたじひめ)」
の神勅によって、御子「稲依別命(いなよりわけ)」と共に、
住んでいた神崎郡建部郷千草嶽(現・東近江市五個荘の箕作山)の地に
日本武尊を「建部大神」として祀ったのが創建とされます。
天武天皇4年(675)に近江の守護神として、現在地へ遷座。
天平勝宝7年(755年)には、「大己貴命(おおなむちのみこと)」が、
奈良の「大神神社」から勧請され、権殿に祀られたと伝わります。
建部大社は多くの皇族や武将達から信仰を受けましたが、
特に源頼朝が「平治の乱」に敗れ伊豆に流される道中、
当社に参拝して前途を祈願し、後に大願成就したことは「平治物語」に記されています。
頼朝は源氏再興の宿願を果たし、再び社前で祈願し、多くの神宝と神領を寄進しました。
このことから、建部大社は、出世開運の神としても信仰されています。
 二ノ鳥居と参道
二ノ鳥居と参道
二ノ鳥居と参道
一ノ鳥居から続く参道を左に折れると二ノ鳥居があります。石灯籠が並ぶ玉砂利の参道を進むと、幅広い神門に至ります。(建部大社H.Pより)

建部大社について
御祭神
日本武尊
御神徳:開運・出世・必勝・厄除・災難除
大己貴命
御神徳:縁結び・商売繁盛・家内安全・病気平癒・醸造
当社は、古くから建部大社や建部大明神と呼ばれ、延喜式内社であると同時に、近江国の一之宮として広く崇敬されてきた歴史ある神社です。
当社の祭神である日本武尊は、熊襲兄弟を倒し、東夷を平定し、30歳で亡くなりました。父である景行天皇は尊の功績をたたえて建部を定め、景行天皇46年(西暦116年)に神勅により御妃 布多遅比売、御子 稲依別王が住んでおられた神前郡武部、鈴鹿郡の能褒野の郷千草嶽に社殿を創建し、日本武尊を斎祭られました。
その後、天武天皇の時代に瀬田に奉還され、大和の国の一の宮の大神神社の大己貴命を奉祀して以来、近江一宮として尊崇されてきました。歴代の皇族や武将たちの信仰を受け、特に源頼朝が平家に捕らわれた際、当社に参拝して前途を祈願したことが平治物語に記されています。
頼朝は後に源氏再興の宿願を果たし、再び社前で祈願し、多くの神宝と神領を寄進しました。以来、当社は出世開運、除災厄除、商売繁盛、縁結び、医薬醸造の神として信仰を集めています。(建部大社H.Pより)

納涼船幸祭
大津三大祭のひとつであり、伝統的な夏の神事です。
毎年8月17日に行われ、その起源は平安時代にさかのぼります。日本武尊が東国にて船団を率い海路を渡った故事に基づいています。瀬田川を海路に見立て、神輿を船に乗せて巡行をする「船渡御神事」の進行にあわせて奉納花火が打上げられます。
幻想的な灯篭の光が湖面を照らし、古代からの伝統を感じることができる貴重な行事です。(建部大社H.Pより)
 幻の千円札
幻の千円札
幻の千円札
昭和二十年八月、日本で初めて作られた千円札。当時の最高紙幣として発行されました。図柄は御祭神である日本武尊と当社の本殿が使用されています。発行された枚数が極めて少なく幻の千円札といわれています。

一、ヤマトタケルの西征ヤマトタケルノミコトは父(第十二代 景行天皇)の御子、小唯命(オウスノミコト)として生まれます。父はオウスノミコトに朝廷に従わない西国の九州・熊襲健(クマソタケル)兄弟を征伐するように命じました。熊襲健兄弟の館を見つけたミコトは、女装をして熊襲の女達に混じり宴に紛れ込み。熊襲兄弟酔ったところで忍ばせていた短剣で熊襲兄弟を討ちました。 熊襲兄弟を討った事から強者の称号である「タケル」の名をもらい、日本武尊(ヤマトタケル)の名で呼ばれるようになりました。

二、ヤマトタケルと草薙の剣西国征伐から戻ったヤマトタケルノミコトに景行天皇は東国征伐を命じます。途中、伊勢神宮に立ち寄り祖母の倭姫宮(ヤマトヒメ)から 神剣、天叢雲剣(アメノムラクモノツルギ)と火打具を授かりました。駿河国に達したミコトに国造(クニノミヤツコ)たちは「沼に住む荒ぶる神に困っております」と、野に誘い出され四方から火を放たれました。 退路を断たれミコトは、から倭姫(ヤマトヒメ)から授かった神剣で草を薙ぎ払い、火打具で向かい火を放って野火から脱出します。後に火で焼いたことからこの地を焼津(やいず)(*静岡県)といい、草をなぎ払った神剣は草薙の剣(クサナギノツルギ)と呼ばれるようになりました。
三、オトタチバナヒメの入水
更に東へ進んだヤマトタケルノミコトは、次に相模の国から船で海路を進み上総の国へ渡ろうとしました。しかし、海が荒れ船を進めることが出来ずにいると、同行していたオトタチバナヒメが、「私が海に入って海の神を鎮めましょう」といって自ら荒波に身を投じたのです。すると、たちまち荒れ狂っていた海は、静まり対岸に着くことができました。

四、ヤマトタケルと伊吹山の神
東国を平定し尾張の国に戻ってくると、今度は伊吹の山に悪い神がいると聞き付けたヤマトタケルノミコトは、神剣:草薙の剣をミヤスビメに預けて討伐に向かいました。伊吹山に登る途中、牛ほどの大きな白い猪に出会い「これは山の神の使いだな!帰り道で相手になってやろう」と大きな声で威嚇してやり過ごしました。すると突然激しく雹(ひょう)が降り出し行く手をはばまれます。実は白い猪は山の神の使いではなく、山の神だったのです。怒りを買い雹に打たれて衰弱したミコトは、やっとの思いで山を脱出し故郷の大和の国を目指します。
五、ヤマトタケルと白鳥伝説
大和の国を目指し歩き続けたヤマトタケルノミコトは、「足が三重(ミエ)曲がり固い餅のようだ」と歎いた事からその地を三重(みえ)と言われるようになりました。更に体調を悪くしたミコトは、国しのびの歌を詠みます。
「倭は国のまほろば たたなづく青垣 山隠れる倭うるはし」と詠み、
伊勢の能褒野(三重県鈴鹿市)でついに力尽き息を引き取ります・・・
妻や子供たちが駆けつけると、ミコトの魂は白鳥となり能褒野から河内の志紀(大阪羽曳野)へと飛び立ちました。
今も白鳥伝説として語り継がれています。
 建部大社のあゆみ
建部大社のあゆみ

 神門
神門
境内地と神域の境いを示す神門、手水舎と同じく檜皮葺屋根です。
 手水舎
手水舎
 御神木の三本杉と拝殿
御神木の三本杉と拝殿
建部大社の御神紋にもなっている御神木の三本杉は、
755年に「大巳貴命」を「権殿」へと奉祀された際に「一夜にして成長した」
との伝説が伝わっています。

建部大社 拝殿
天武天皇の御代白鳳4年(675年)今から約1300年程前に、この瀬田の地へと遷し祀られました。近江国を守護する神社として大切に守られてきました。

拝殿は間口三間二尺・奥行三間二尺の入母屋造で、
本殿・権殿共用の拝殿とされています。
 本殿・権殿
本殿・権殿
主神を祀る本殿と、権殿は同形式の一間社流造で並列して鎮座します。
ともに間口一間一尺、奥行一間の造りとなります。
拝殿と本殿の間には幣殿のような屋根付きの参拝所がみられます。

本殿・権殿
正面左側が本殿 日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀り、右側は大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る権殿(ごんでん)です。

左側の本殿は日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀り、
見切れてしまっている、右側には大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る権殿が並びます。

御本殿の背後には特別天然記念物の「菊花石」と、
天然記念物の「さざれ石」が安置されています。
特に「菊花石」は、菊の紋様をおもわせる自然の化石で、
これほど鮮明で大きなものは珍しいといわれています。
 菊花石
菊花石
特別天然記念物
菊花石(きっかせき)
菊紋といえば花びらが16枚で八重菊を家紋にしたものが、天皇家の御紋として知られています。このすばらしい菊の紋様が神秘な力の働きで自然石から放射状にのび、出来たものが菊花石であります。非常に縁起のよいものとされ、神秘的な力が感じられます。

 さざれ石
さざれ石
天然記念物
さざれ石
国家「君が代」に詠まれている「さざれ石」は、もともと小さな石の意味であり、長い年月をかけて石灰岩が溶けて凝固し、大きな巌の様になったものです。この「巌となったさざれ石」は神聖な力により作られたと信じられており、神霊の宿る石として繁栄の象徴とされています。
 境内 拝殿と三本杉
境内 拝殿と三本杉
摂社・末社
日本武尊の御妃・御子が社をもうけ、尊の神霊を鎮め祀られたのが起源とされています。本殿を囲むように左右に八つの社があり、上座4社には日本武尊の父母である景行天皇と皇后、御妃と御子が祀られ、下座4社には日本武尊の遠征に付き従った家臣の方々をお祀りしています。
 大政所神社・聖宮神社
大政所神社・聖宮神社
右、聖宮(ひじりのみや)神社の御祭神は「景行天皇(日本武尊の父)」を祀る。
左、大政所(おおまんどころ)神社の御祭神は
「播磨稲日大郎姫命(景行天皇の皇后・日本武尊の母)」を祀ります。
 蔵人頭神社・行事神社
蔵人頭神社・行事神社
蔵人頭神社の御祭神は「七掬脛命」・行事神社の御祭神は「吉備臣武彦・大伴連武日」
手前2社はそれぞれ日本武尊の家臣をお祀りします。
 藤宮神社・若宮神社・弓取神社・箭取神社
藤宮神社・若宮神社・弓取神社・箭取神社
左より、藤宮(ふじのみや)神社の御祭神「布多遅比売命」・
若宮神社の御祭神「建部稲依別命」・弓取神社の御祭神「弟彦公」・
箭取神社の御祭神は三柱「石占横立・尾張田子之稲置・乳近之稲置」です。
 武富稲荷神社(右)・八柱神社(左)
武富稲荷神社(右)・八柱神社(左)
武富稲荷神社の御祭神は「稲倉魂命」
八柱神社は「藤時平・融大臣・事代主命・市杵嶋姫命・素盞男命・豊玉彦命・櫛名多姫命」
の八柱をお祀りします。
 宝物殿
宝物殿
内部には女神像(平安時代作・重要文化財)や、
日本武尊と建部大社が描かれた日本初の千円紙幣などを見ることが出来ます。
宝物殿の拝観は要予約(※拝観料 300円)

日本遺産 滋賀
琵琶湖とその水辺景観、祈りと暮らしの水遺産
人々は、琵琶湖の水や山からの湧き水を生活の中に巧みに取り入れ、水を汚さないように工夫をしながら生活を営んできました。また、水を神として敬い、信仰の対象としてきました。さらに、湖辺の集落では、湖魚を用いた独特の食生活や伝統的な漁法が育まれ、独特の景観を生み出してきました。滋賀では、このような水と人々との関わりが今も息づき、大切に受け継がれています。

 社務所
社務所
建部大社(たけべたいしゃ)
鎮座地 滋賀県大津市神領一丁目16-1
電話番号 077-545-0038
創建 景行天皇46(116)年
社格 式内社(名神大社)・近江国一宮・官幣大社
駐車場 参道周辺に大型駐車場完備(約70台)
拝観時間 5時〜17時
その他 宝物殿9時〜16時(拝観料300円)*拝観は事前に要予約
 建部大社 御朱印
建部大社 御朱印