山梨百名山
すべての山に思い出がある、百名山
| 山梨百名山 | |
|---|---|
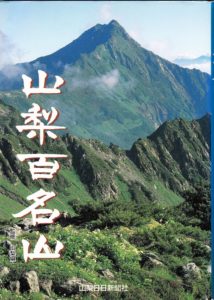 |
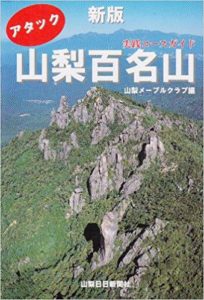 |
| ■定価:2400円+税 ■発行: 山梨日日新聞社 ■山梨県が選定した山梨の百名山を四季折々のカラー写真で紹介。登山道の略図やコースガイドも付記。 |
|
山梨百名山
山梨百名山(やまなしひゃくめいざん)は、1997年、山梨県によって選定された県内の名山100選である。一般公募と市町村推薦であがった候補の中から、選考委員会によって、県民に親しまれている・全国的な知名度がある・歴史や民俗との関わりあるなどの基準で選ばれたとされる。
「大菩薩・道志山系(27山)」「南アルプス山系(25山)」
「富士・御坂山系(20山)」「八ヶ岳・秩父山系(28山)」からなります。
登頂した山は画像を掲載、山名・画像から詳細記事へリンク
山岳信仰(神社・寺院)関連史跡なども掲載しております。
所在地と(経路)をクリックでGoogleマップ
標高(地図)をクリックで地理院地図(電子国土Web)
をそれぞれご覧頂けます。
2024年10月20日の「鶏冠山」で100座 完登しました。
山梨百名山
大菩薩・道志山系
大菩薩付近、桂川流域など県東部の山々
大菩薩連峰の盟主「大菩薩嶺」2057mと「小金沢山」2014m以外、他は全て1000m級の山々、低山の連なりですが、谷は深く豊富な水量で、東京都や神奈川県の水源となっています。妙心上人が修行をしかつては信仰の山だった「御正体山」、郡内領主小山田氏の山城があった「岩殿山」、眼下にリニアモーターカー新実験線施設が見える「高川山」、山梨県・東京都の境にありその名の通りピークが三つある「三頭山」、鎮西八郎為朝と白縫姫の伝説がある「滝子山」、頂上に神社があり社の後ろに石という字に似た巨岩のある「石割山」、山頂が広く開けて富士山を撮る写真家に人気の「鳥ノ胸山」、山頂に桜が植えられ4月下旬が見頃の「百蔵山」など26山があります。大室山・御正体山が上級者向。ただすべての山が日帰り可能という比較的身近な山々です。中央線沿いの山々は、アクセスの良さもあってハイカーに人気が高いようです。桜、新緑から秋へと眺めの良い山揃いでもあります。
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 小金沢山(こがねざわやま) | 雁ガ腹摺山(がんがはらすりやま) |
 |
 |
 |
| 北都留郡丹波山村 | 大月市大月町 | 大月市七保町 |
| ■標高2057m(地図) ■─ ■─ ■2018年9月23日 |
■標高2014m(地図) ■─ ■ ■2023年8月4日 |
■標高1874m(地図) ■─ ■─ ■2023年8月4日 |
| 4 | 5 | 6 |
| 大蔵高丸(おおくらたかまる) | 滝子山(たきごやま) | 笹子雁ガ腹摺山(ささこがんがはらすりやま) |
 |
 |
 |
| 大月市大月町真木 | 大月市笹子町 | 大月市笹子町黒野田 |
| ■標高1781m(地図) ■─ ■─ ■2023年8月4日 |
■標高1620m(地図) ■─ ■─ ■2023年10月21日 |
■標高1358m(地図) ■─ ■─ ■2022年10月29日 |
| 7 | 8 | 9 |
| 源次郎岳(げんじろうだけ) | 棚横手山(たなよこてやま) | 本社ヶ丸(ほんしゃまる) |
 |
 |
 |
| 甲州市塩山中萩原 | 甲州市勝沼町菱山 | 大月市笹子町 |
| ■標高1477m(地図) ■ ■─ ■2023年8月5日 |
■標高1306m(地図) ■─ ■─ ■2023年8月5日 |
■標高1631m(地図) ■ ■─ ■2021年10月8日 |
| 10 | 11 | 12 |
| 高川山(たかがわやま) | 三頭山(みとうさん) | 権現山(ごんげんやま) |
 |
 |
 |
| 都留市小形山 | 上野原市西原 | 上野原市西原 |
| ■標高976m(地図) ■─ ■─ ■2022年10月29日 |
■標高1531m(地図) ■─ ■─ ■2024年6月14日 |
■標高1312m(地図) ■─ ■─ ■2022年5月28日 |
| 13 | 14 | 15 |
| 扇山(おうぎやま) | 百蔵山(ももくらさん) | 岩殿山(いわどのさん) |
 |
 |
 |
| 大月市七保町 | 大月市七保町 | 大月市賑岡町 |
| ■標高1138m(地図) ■─ ■─ ■2022年5月28日 |
■標高1003m(地図) ■─ ■─ ■2022年5月28日 |
■標高634m(地図) ■─ ■─ ■2022年5月28日 |
| 16 | 17 | 18 |
| 高柄山(たかつかやま) | 倉岳山(くらたけさん) | 九鬼山(くきやま) |
 |
 |
 |
| 上野原市鶴島 | 大月市猿橋町 | 大月市猿橋町 |
| ■標高733m(地図) ■─ ■─ ■2024年6月14日 |
■標高990m(地図) ■─ ■─ ■2019年12月21日 |
■標高970m(地図) ■─ ■─ ■2023年10月21日 |
| 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|
| 二十六夜山(にじゅうろくやさん) | 菜畑山(なばたけうら) | 今倉山(いまくらやま) |
 |
 |
 |
| 上野原市秋山 | 都留市川原畑 | 都留市朝日曽雌 |
| ■標高972m(地図) ■─ ■─ ■2019年12月21日 |
■標高1283m(地図) ■─ ■─ ■2021年7月10日 |
■標高1470m(地図) ■─ ■─ ■2021年7月10日 |
| 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|
| 御正体山(みしょうたいやま) | 石割山(いしわりやま) | 杓子山(しゃくしやま) |
 |
 |
 |
| 都留市大野 | 都留市鹿留 | 富士吉田市大明見 |
| ■標高1681m(地図) ■─ ■─ ■2024年4月20日 |
■標高1413m(地図) ■─ ■─ ■2020年10月24日 |
■標高1598m(地図) ■─ ■─ ■2020年10月24日 |
| 25 | 26 | |
|---|---|---|
| 大室山(おおむろやま) | 鳥ノ胸山(とりのむねやま) | |
 |
 |
|
| 富士河口湖町本栖 | 南都留郡道志村 | |
| ■標高1587m(地図) ■─ ■─ ■2024年4月20日 |
■標高1208m(地図) ■─ ■─ ■2021年7月10日 |
■─ ■─ ■─ ■─ |
南アルプス山系
富士川右岸、南アルプスなど県西部の山々
かつては海底だった地が一転隆起して出来た山々。1億5千万年から8千万年ほど前までアルプスの造山運動は続き、その間に誕生したのだといわれてます。最高峰「北岳」は日本第2位の高峰、キタダケソウなどの固有種が咲く見事なお花畑があるダイナミックな展望の山。南アルプスで最も男性的にそそり立つ「甲斐駒ヶ岳」、穏やかな山容で多くの高原植物が咲く「仙丈ヶ岳」、その名の通りのこぎりの歯のような岩綾を持ち岩登り等の技術が必要な熟達者向き「鋸岳」、地蔵ケ岳・観音岳・薬師岳の三山を主とした山塊「鳳凰山」、日蓮宗の守護神として信仰される七面明神が祀られる「七面山」、レンゲツツジの大群落が咲き誇る初心者OKの「甘利山」、アヤメの群生地として有名な「櫛形山」など27山があります。急峻で手強い山から、誰でも登れる山まで、幅広い登山の対象となる山が連なる山系です。また南部の「笹山」や「笊ケ岳」のようなまだ未開の山もあり愛好者には興味のつきない山系です。
| 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|
| 身延山(みのぶさん) | 七面山(ひちめんさん) | 八紘嶺(はっこうれい) |
 |
 |
 |
| 南巨摩郡身延町 | 南巨摩郡身延町 | 南巨摩郡早川町 |
| ■標高1153m(地図) ■─ ■身延山 久遠寺 ■2017年7月22日 |
■標高1989m(地図) ■─ ■七面山 敬慎院 ■2019年12月6日 |
■標高1918m(地図) ■─ ■─ ■2019年6月1日 |
| 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|
| 山伏(やんぶし) | 十枚山(じゅうまいさん) | 篠井山(しのいさん) |
 |
 |
 |
| 南巨摩郡早川町 | 南巨摩郡南部町 | 巨摩郡南部町福士 |
| ■標高2014m(地図) ■─ ■─ ■2019年6月1日・2020年6月6日・2021年5月23日 |
■標高1726m(地図) ■─ ■─ ■2019年9月1日・2023年12月17日 |
■標高1394m(地図) ■─ ■四ノ位明神 ■2020年4月3日 |
| 51 | 52 | |
|---|---|---|
| 貫ヶ岳(かんがたけ) | 高ドッキョウ(たかどっきょう) | |
 |
 |
|
| 南巨摩郡南部町 | 南巨摩郡南部町 | |
| ■標高897m(地図) ■─ ■─ ■2019年11月23日・2023年12月2日 |
■標高1134m(地図) ■─ ■─ ■2019年11月23日・2023年12月8日 |
■─ ■─ ■─ ■─ |
富士・御坂山系
御坂山地、富士山周辺など県南部の山々
日本最高峰の富士山が最後に噴火したのは1707年の休火山。富士の北から西を取り巻く御坂山塊、天子山塊は太平洋プレートにより押し上げられた山で、火山は富士山のみ。大いなる信仰の山・富士山への登山は、平安時代の富士修験道に始まります。庶民は富士講として江戸の中期頃に盛んに登っていたといいます。ロッククライミングのメッカ、ハイキングコースとしても有名な「三ツ峠山」、甲府からもその姿がよくわかる切り立った円錐形の岩山「釈迦ヶ岳」、本栖湖に迫るように位置し山頂からのダイアモンド富士で人気の「竜ヶ岳」、山名とは異なり立派に樹木に覆われた中山金山跡のある「毛無山」、東海自然歩道のコースでもあり大沢崩れの富士と田貫湖を望む「長者ヶ岳」、戦国時代は最南端の城塞で森林公園となっている「白鳥山」など19山があります。「黒岳」周辺など、御坂山塊にはブナの自然林があり目につきます。これこそ今後守っていきたい貴重な財産です。みなさんも大切に守ってください。
| 71 | 72 | |
|---|---|---|
| 三石山(みついしやま) | 思親山(しんしざん) | |
 |
 |
|
| 南巨摩郡南部町上佐野 | 南巨摩郡南部町内船 | |
| ■標高1173m(地図) ■─ ■─ ■2020年10月30日 |
■標高1031m(地図) ■─ ■─ ■2020年10月30日 |
■─ ■─ ■─ ■─ |
八ヶ岳・秩父山系
八ヶ岳、奥秩父など県北部の山々
八ヶ岳は本州を二分するフォッサマグナの中央に噴出した第三紀の火山です。また奥秩父は太平洋プレートに押し出されたシワで、生成過程のまったく違う山なのです。登山としては奥秩父の方が先に開け、八ヶ岳は小海線開通以降(昭和10年)。何れの山も修験者の信仰登山の場でもありました。山頂に二つの岩塔が立ち八ヶ岳修験道の中心だった「権現岳」、奥秩父西端の名峰、6月のシャクナゲが美しい「瑞牆山」(みずがきやま)、甲信国境にたたずむ八ヶ岳の主峰「赤岳」、八ヶ岳連峰の南端に位置し原生林が安らぎを与えてくれる「編笠山」、奥秩父の盟主にして古い信仰の歴史ある「金峰山」、奥秩父の中心に位置する「甲武信ヶ岳」(こぶしがたけ)、武田信玄の菩提寺、恵林寺の開祖夢窓国師が修行した「乾徳山」、東沢と鶏冠谷に挟まれた人を拒む急峻な「鶏冠山」、日本三大峠の一つとして有名な雁坂峠の西北「雁阪嶺」など28山があります。戦国時代の歴史をも秘めた魅力的な山々です。
| 91 | 92 | 93 |
|---|---|---|
| 小楢山(こならやま) | 茅ヶ岳(かやがたけ) | 曲岳(まがりだけ) |
 |
 |
 |
| 山梨市牧丘町柳平 | 甲斐市亀沢 | 甲斐市上芦沢 |
| ■標高1713m(地図) ■─ ■─ ■2023年7月22日 |
■標高1704m(地図) ■─ ■─ ■2021年4月23日 |
■標高1642m(地図) ■─ ■─ ■2021年4月23日 |
| 94 | 95 | 96 |
|---|---|---|
| 黒富士(くろふじ) | 太刀岡山(たちおかやま) | 羅漢寺山(らかんじやま) |
 |
 |
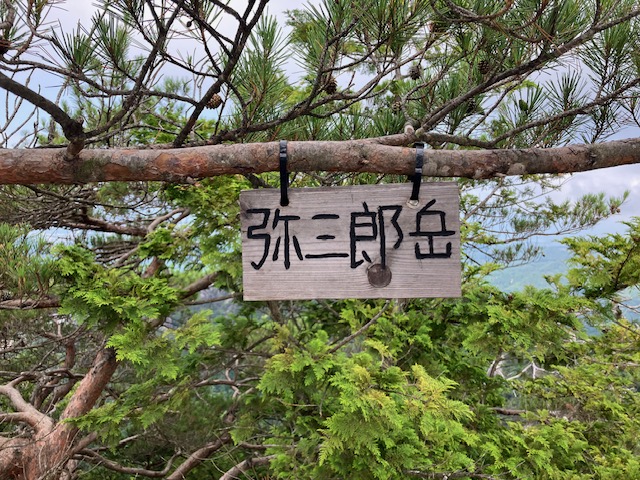 |
| 甲府市御岳町 | 甲府市草鹿沢町 | 甲斐市千田 |
| ■標高1635m(地図) ■─ ■─ ■2021年4月23日 |
■標高1295m(地図) ■─ ■─ ■2021年4月23日 |
■標高1058m(地図) ■─ ■─ ■2023年7月22日 |
| 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|
| 帯那山(おびなやま) | 要害山(ようがいざん) | 兜山(かぶとやま) |
 |
 |
 |
| 山梨市切差 | 甲府市上積翠寺町 | 山梨市上岩下 |
| ■標高1422m(地図) ■─ ■─ ■2022年8月10日 |
■標高780m(地図) ■─ ■要害山城跡 ■2022年8月10日 |
■標高913m(地図) ■─ ■─ ■2022年8月10日 |
| 100 | ||
|---|---|---|
| 大蔵経寺山(だいぞうきょうじやま) | ||
 |
||
| 笛吹市春日居町 | ||
| ■標高716m(地図) ■─ ■─ ■2022年8月10日 |
■─ ■─ ■─ ■─ |
■─ ■─ ■─ ■─ |

































































