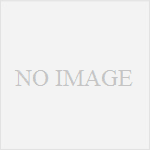誉田八幡宮(こんだはちまんぐう)・大阪府羽曳野市誉田

大阪府羽曳野市誉田、「誉田八幡宮(こんだはちまんぐう)」
旧社格は府社、誉田御廟山古墳(応神天皇陵)の南に隣接して鎮座します。
欽明天皇20年(559年)に任那の復興を目指した欽明天皇によって、
応神天皇陵前に神廟が設置されたことをもって創建としています。
このことから最古の八幡宮を称しています。
八幡神(やはたのかみ・はちまんしん)、誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、
源氏の氏神とされることから、古来より源氏姓を名乗る歴代の将軍をはじめ、
武家の信仰が厚い神社です。

奈良時代には行基によって神宮寺の長野山護国寺も創建されます。
永承6年(1051年)の後冷泉天皇行幸の際に、元の鎮座地から1町ほど南の現在地に遷座。
神宮寺の長野山護国寺は搭頭十五坊を誇っていたが(誉田八幡宮は社人十三家)、
明治初年の廃仏毀釈により大半の建物が取り壊され、現在は南大門のみが残ります。


譽田八幡宮
譽田八幡宮は応神天皇(第15代 譽田別尊:ほむたわけのみこと)、仲哀天皇(第14代)、神功皇后を主祭神とし、永享5年(1433)に足利義教(室町幕府第6代将軍)が奉納した「譽田宗廟縁起絵巻」には、欽明天皇(第29代)の勅定によって応神天皇の陵の前に営まれた社殿を、後冷泉天皇(第70代)の頃(1045~68)になって、南へ1町(約109メートル)離れた現在の場所に造り替えたことが伝えられています。
鎌倉時代から室町時代にかけては、源氏の氏神である八幡神を祀る社として、将軍家をはじめとする武士の信仰をあつめ、社殿の造営や宝物の奉納がおこなわれましたが、戦国期にはたびたび合戦場となって兵火にかかることもありました。
その後、豊臣秀吉から社領の寄進を受け、豊臣秀頼が片桐且元に命じて社殿の再建をおこないました。江戸時代になってからは、幕府による保護のもとに社殿の再建と整備がすすめられました。
享和元年(1801)の「河内名所図会」や天保9年(1838)の古図には、本社や摂社、神宮寺の堂宇など多くの建物が並び、参詣の人々が訪れるようすが描かれています。
源頼朝の寄進と伝えられる塵地螺鈿金銅装神輿(国宝)や、譽田丸山古墳から発見された金銅製透彫鞍金具(国宝)、「譽田宗廟縁起絵巻」(重要文化財)、「神功皇后縁起絵巻」(重要文化財)など、多くの貴重な文化財を社宝としています。

屋根の吹き替え工事中の「拝殿」
誉田八幡宮の建物は、豊臣家による社殿の再建が八割方進んだところで放置された後、
徳川家によって仕上げられたので、屋根などに三ツ葉葵の紋が付けられているのが見られる。
誉田八幡宮 拝殿
東面する入母屋本瓦葺で間口十一間、奥行三間の細長い木造建築でいわゆる割拝殿の形式であって正面中央部を拝所とし向拝(ごはい)部分は、唐破風造りで蛇腹天井となっている。 この建物は、慶長十一年(1606)に豊臣秀頼が普請奉行に片桐且元を任じて再建させたものであるが、完成直前に大阪の役(冬の陣、夏の陣)が勃発したため八割方でき上がったまま放置されていた。その後、徳川家光が再建工事を続行して寛永年間の初期に竣工したものと考えられている。 この拝殿は、天井が張られていないので木組のありさまが観察することができる。 徳川家によって最後の仕上げがなされたので、三ツ葉葵の定紋が付けられている。


 絵馬堂
絵馬堂
応神天皇は清和源氏や桓武平氏をはじめとする
全国の武士に武運の神として崇敬された八幡神であり、当社は最古の八幡宮とされています。
また、八幡神は源氏の氏神でもあるので源頼朝が社伝を造営するなど、
源氏姓を名乗る歴代将軍の信仰も厚かったようです。
 恵比寿社
恵比寿社
参道右にある恵比寿社の例祭は1月9日に執り行われ、
当日は福よせ・福笹が授与されます。
 姫待稲荷社
姫待稲荷社

誉田林古戦場址
誉田八幡宮の付近は、南北朝から室町戦国の各時代を経て、江戸初期の元和年間にかけて戦略上の要地であったため再三古戦場の舞台となったところである。
すなわち、南北朝初期の正平年間には、北朝方の細川兄弟の軍と楠木正行の間で合戦が行われ、室町中期の享徳年間には畠山政長と義就の間で再三にわたり誉田合戦が行われた。すこし降って、永正元年(1504)には、前記の孫にあたる畠山稙長(タネナガ)と義英との間で合戦の後で和議となり誉田八幡宮「社前の盟約」が結ばれたのもこの境内であった。大阪夏の陣の折には、大阪方の武将薄田隼人正もこの境内に大陣を置きこの地より出撃して道明寺近辺で、討死をとげたのである。

元和元年(1615)大坂夏の陣では、
豊臣秀頼と淀殿らが守る大阪城を、徳川家康らの軍勢が攻め込みました。
この戦いの局地戦が、ここ羽曳野市誉田、藤井寺市道明寺付近にかけての一帯でも行われ、
「道明寺の戦い」と呼ばれています。
道明寺の戦いでは、豊臣方の後藤又兵衛(基次)や薄田兼相などの武将が討ち死にし、
徳川方の勝利で終わっています。

御朱印