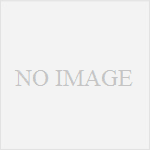河内国一宮 枚岡神社・大阪府東大阪市出雲井町

大阪府東大阪市出雲井町に鎮座する「枚岡神社(ひらおかじんじゃ)」
延喜式では式内社(名神大社)にして「河内国一宮」、旧社格は官幣大社です。
御祭神は4柱、御本殿4棟(第一・第二・第三・第四殿)に各1柱づつ祀られています。
第一殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと)・主祭神 中臣氏祖神
第二殿 比売御神(ひめみかみ)・天児屋根命の妻神
第三殿 経津主命(ふつぬしのみこと)・ 香取神宮 御祭神
第四殿 武甕槌命(たけみかづちのみこと)・鹿島神宮 御祭神
枚岡神社は大阪府東部の生駒山地西麓に鎮座します。
現在、「枚岡神社本宮」を祀る「神津嶽(268m)」を神体山とする山岳信仰に由来し、
中臣氏の祖の天児屋根命を主祭神とする中臣氏の氏神として知られています。
中臣氏から分かれた藤原氏が氏神として春日大社を創建した際には、
祭神4柱のうち2柱として当社の天児屋根命・比売神の分霊が勧請されており、
それに由来して「元春日」とも呼ばれています。
御本殿は春日大社と同様に春日造の4棟からなり、
東大阪市指定有形文化財に指定されています。
また、特殊神事のうち「粥占神事」が大阪府選択無形民俗文化財、
「注連縄掛神事」は東大阪市指定無形民俗文化財に指定されている。
 石鳥居
石鳥居
駐車場の手前にある石鳥居は皇紀2600年を記念して、
昭和15年に新築されました。
一の鳥居はここより数百メートル西にあり、昔の東高野街道に面して建てられています。
ここからが枚岡神社への参詣道となっています。
 ニノ鳥居
ニノ鳥居
ニノ鳥居
現在の鳥居は昭和54年竣工。明治19年、昭和9年に改築を経て現在に至っております。鳥居の額面は、大正4年に奉納されたもので、この年には伏見宮女王殿下御参拝、又大嘗祭奉告祭に勅使がつかわされ祭礼がおこなわれました。現在の鳥居は平成令和の大造営(平成30年9月竣工)で新たに甦りました。

枚岡神社
創祀
枚岡神社の創祀は、皇紀前まで遡り、初代天皇の神武天皇が大和の地で即位される3年前と伝えられています。
神武御東征の砌、神武天皇の勅命を奉じて、天種子命(あめのたねこのみこと)が平国(くにむけ)(国土平定)を祈願するため天児屋根命・比売御神の二神を、霊地神津嶽(かみつだけ)に一大磐境を設け祀られたのが枚岡神社の創祀とされています。御由緒
枚岡神社は、永く神津嶽にお祀りされましたが、孝徳天皇の白雉元年(はくちがんねん)(650年)9月16日に、平岡連らにより山麓の現地へ奉遷されたと伝えられています。神護景雲(じんごけいうん)2年(768年)に、天児屋根命・比売御神の二神が春日山本宮の峰に影向せられ、春日神社(現在の春日大社)に祀られました。このことから当社が「元春日(もとかすが)」とよばれる由縁であります。
その後、宝亀(ほうき)9年(778年)春日神社より、武甕槌命・斎主命の二神を春日神社より迎え配祀し四殿となりました。
大同元年(806年)には60戸の封戸を充てられ、貞観元年(856年)天児屋根命の神階は正一位の極位を授かり、延喜式神名帳では名神大社に列せられました。その後勅使参向のもとお祭りが行われ、又随時、祈雨、祈病平癒の奉幣に預かる等優遇を受け、寛治5年に堀河天皇が参拝されるなど、勅旨により創始されたことにより朝廷から特別な尊崇をうけたことがうかがわれます。

御祭神
主祭神として祀られている天児屋根命(あめのこやねのみこと)は、「日本書紀」神代巻に「中臣の上祖(とおつおや)」「神事をつかさどる宗源者なり」と記され、古代の河内大国に根拠をもち、大和朝廷の祭祀をつかさどった中臣氏の祖神で、比売御神(ひめみかみ)はその后神です。
経津主命(ふつぬしのみこと)・武甕槌命(たけみかづちのみこと)は、香取・鹿島の神で、ともに中臣氏との縁深い神として知られています。

第1殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと)
天兒屋命・天之子八根命・天子屋根命とも書き、太詔戸命・櫛眞智命中臣の神とも称え奉られます。
天の岩戸開きに功績をあげられますが、はじめてお祭りを行い、祝詞を奏上された事から「神事宗源(しんじそうげん)」の神と称えられています。
天孫降臨の神話では、瓊々杵尊(ににぎのみこと)に御供仕え奉った神々の中でも、特に重責を担った神であり、天照大御神(あまてらすおほみかみ)・高皇産霊神(たかみむすひのかみ)から、皇孫を助け斎ひ護るようにとの神勅により、その重責をはたし皇運の基礎を固めきづかれた事から、「天孫輔弼(てんそんほひつ)」の神とも称えられています。第2殿 比売御神(ひめみかみ)
諸説があり詳細は不明ですが、天美豆玉照比売命(あめのみづたまてるひめのみこと)とも称えられ天児屋根命の后神で、常に夫神を助けられ内助の功績多く、御子神天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)を強く賢く育てられる等、良妻賢母、女性の鑑と仰がれています。
第3殿 武甕槌命(たけみかづちのみこと)
鹿島神宮の御祭神。建御雷之男神(タケミカヅチノオノカミ)、建御雷神建御賀豆知命、布都御魂神と称え奉られています。
神話の中の国譲りにおいて、高天原の最高司令神の名で地上の国を平定する切り札として出雲国に派遣され、見事にその役を果たされ、国の平定における武力と権威の象徴ともいうべき神様です。第4殿 経津主命(ふつぬしのみこと)
香取神宮の御祭神。比古自布都命(ひこじふつのみこと)・斎主命(いわいぬしのみこと)・伊波比・斎ノ大人とも称え奉られています。
武甕槌命と同じく、神話「国譲り」において出雲国に派遣され、見事にその役を果たされた神様で、武運守護の大神と仰がれています。

特殊神事
粥占神事(かゆうらしんじ)
1月11日
小正月の年占い神事。かつては1月15日に行われたが、現在は1月11日に斎行されて15日に結果が発表される(粥占奉賽祭)。神事では、米5枡・小豆3枡を大釜で炊き、その中に占竹53本1束を吊り下げて入れ、竹の中に入った小豆粥の状態でその年の豊作を占う。また黒樫の占木12本(閏年は13本)を竈に入れて、木の焦げ具合で晴雨を占う。『河内鑑名所記』にも神事の様子が記述される。大阪府選択無形民俗文化財に選択されている。
注連縄掛神事(お笑い神事)(しめかけしんじ)
12月23日
笑いにより春を誘う神事。かつては粥占神事に先立つ1月8日に行われた。神事では、石段下の注連縄柱に大きな注連縄を掛け渡し、その下で神職と氏子総代が春の到来を念じて高笑いを行う。東大阪市指定無形民俗文化財に指定されている。(Wikipediaより)
 斎館
斎館
斎館
昭和10年竣工の建物。それまでも建物は存在しましたが、昭和12年貞明皇太后行啓をお迎えするにあたり建替えられました。
 枚岡神社 参道
枚岡神社 参道
枚岡神社
所在地 大阪府東大阪市出雲井町7番16号
電話番号 072-981-4177
H.P http://hiraoka-jinja.org/index.html
アクセス 近鉄奈良線『枚岡駅』下車、徒歩すぐ
駐車場 タイムズ枚岡神社・約40台(午前9時から午後4時)駐車料金 平日・当日1日最大料金500円(24時迄)
土日祝・当日1日最大料金800円(24時迄)
30分以内 無料 (ただし30分以降30分 200円)

社伝によると創建は神武天皇即位前3年(紀元前663年)と伝わります。
天児屋根命を祖とする一族は「平岡連(ひらおかむらじ)」と呼ばれ、
後に中臣氏の氏神となりました。
中臣氏の祖神であることから分家した藤原氏の氏神としても信仰されています。
奈良に「春日大社」を創建した際には「枚岡神社」より分霊し勧請されていることから、
枚岡神社は「元春日」とも、
また天児屋根命を祖とする一族が「平岡連」と呼ばれるようになったことから
「元春日平岡大社」とも呼ばれています。
御神徳は国家安泰・家内安全・夫婦和合・開運招福。
 枚岡神社 拝殿
枚岡神社 拝殿
式内社 枚岡神社(ひらおかじんじゃ)
別称 平岡神社・元春日社
鎮座地 〒579-8033 大阪府東大阪市出雲井町7-16 旧河内国 茨田郡
旧社格 官幣大社 (現別表神社)河内国一ノ宮
式内社 河内國河内郡 枚岡神社四座 並名神大 月次相嘗新嘗
御祭神 (第一殿) 天児屋根大神・(第二殿) 比売大神
(第三殿) 経津主命・(第四殿) 武甕槌大神
例祭日 二月一日〈神事〉里祭、粥占神事、平国祭くにむけまつり
由緒
神武天皇の侍臣で 中臣氏の祖天種子命が、神武天皇の命で神津岳の頂きの平らな岡に祖神を祭ったのが起源という。河内に栄えた中臣氏支流平岡連の氏神であり、白雉元年(六五〇) 平岡連らによって山頂から現在地に遷された。 奈良の春日大社の創祀にあたっては、この社から天児屋根命と比売神が勧請されており、そのため元春日とも称さた。

拝殿
明治12年に新築されました。平成の修造で檜皮葺きから、銅板葺きに葺き替えられました。正面に掲げられた神額は、三條實美公揮毫であります。
 中門・透き塀
中門・透き塀
中門・透き塀
明治12年に改築、明治38年に現在の場所に移設され、昭和26年、平成3年、平成令和の大造営(令和2年9月竣工)に修復され現在に至っています。
 御本殿
御本殿
御本殿
現在の御本殿は、文政9年(1826)に、近郡の氏子の奉納により造営されました。それより以前、『御神徳記』によりますと、天喜4年(1056)と宝治元年(1247)に焼亡し、其の都度造営され、文明9年(1477)にも近郡の氏子により造営されたと記されています。また、天正7年(1579)年9月、織田信長の兵火により類焼をうけ、本殿以下諸建物が焼失しましたが、慶長7年(1602)豊臣秀頼公が社殿の造営をし立派に復旧しました。その後、徳川の時代にはいり、当社に対する崇敬は薄れて衰退を余儀なくされましたが文政9年に造営がなされ、その後屋根の葺き替えや塗替え修理がおこなわれ、最近では平成令和の大造営(令和2年9月竣工)で新しく生まれ変わりました。
建築様式は、枚岡造(王子造)と呼ばれ四殿並列極彩色の美しい神社建築です。(市指定文化財)
 粥占神事 案内板
粥占神事 案内板
 鶏鳴殿
鶏鳴殿
鶏鳴殿
社務所として、また御祈祷の控室や結婚式の控室・会食会場、各種会議などの場として使われています。
 授与所
授与所
授与所
昭和10年に新築されました。元々この場所には奏楽舎がありました。現在は、御札御守り等の授与所になっています。石垣の上に建てられており、裏にはお滝があって古くより禊場となっています。
 末社 一言主神社
末社 一言主神社
末社 一言主神社
一言願えばその願いを叶えてくれると言われています。
一言願札に願いをお込めください。
 摂社 若宮神社
摂社 若宮神社
摂社 若宮神社
ご本社の御子神様をお祀りしており水神ともいわれています。
社の後方にはご神水が湧き出る「出雲井」があり、参道からご神水をお受けいただけます。
 末社 天神地祇社
末社 天神地祇社
末社 天神地祇社(てんしんちぎしゃ)
明治初年まで境内にお祀りされていた十九社の末社や、氏子地域内で祀られていた神社が合祀されています。
 天神地祇社にお祀りしている御祭神
天神地祇社にお祀りしている御祭神
 枚岡神社 御朱印
枚岡神社 御朱印